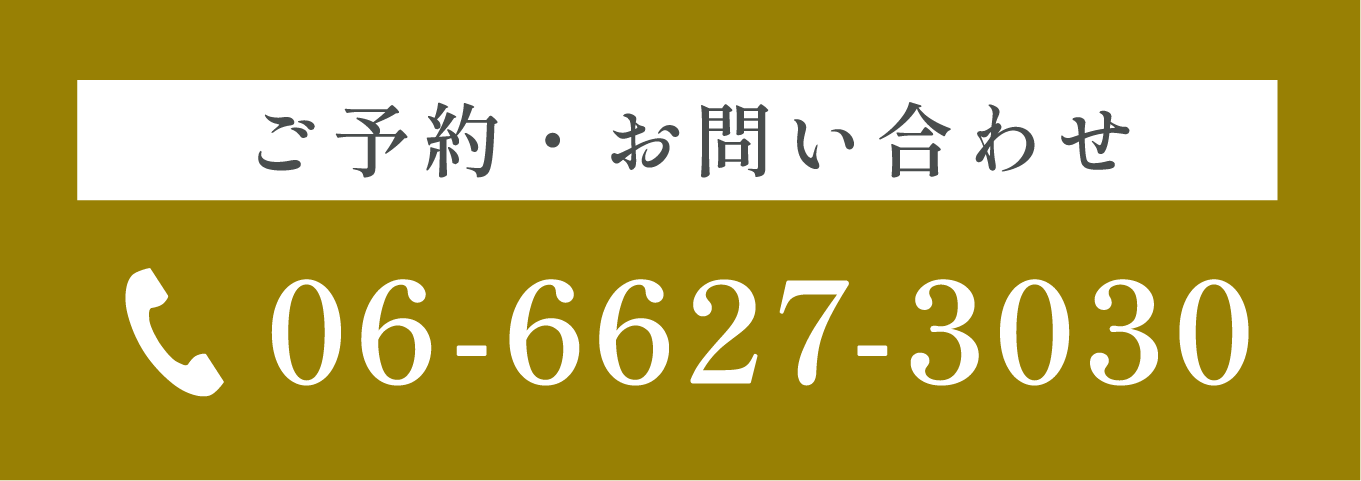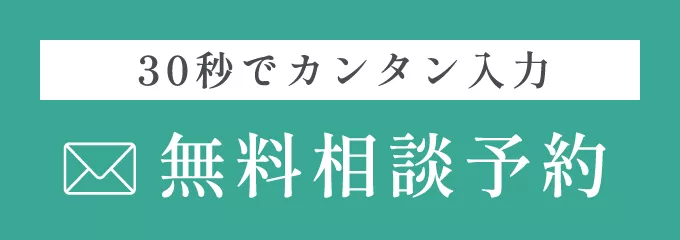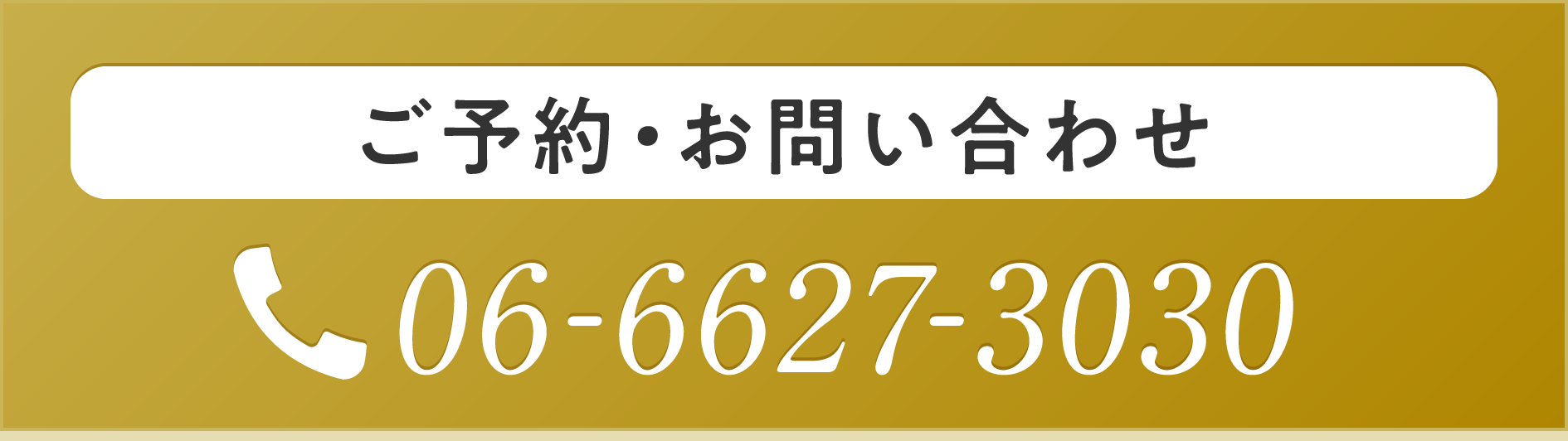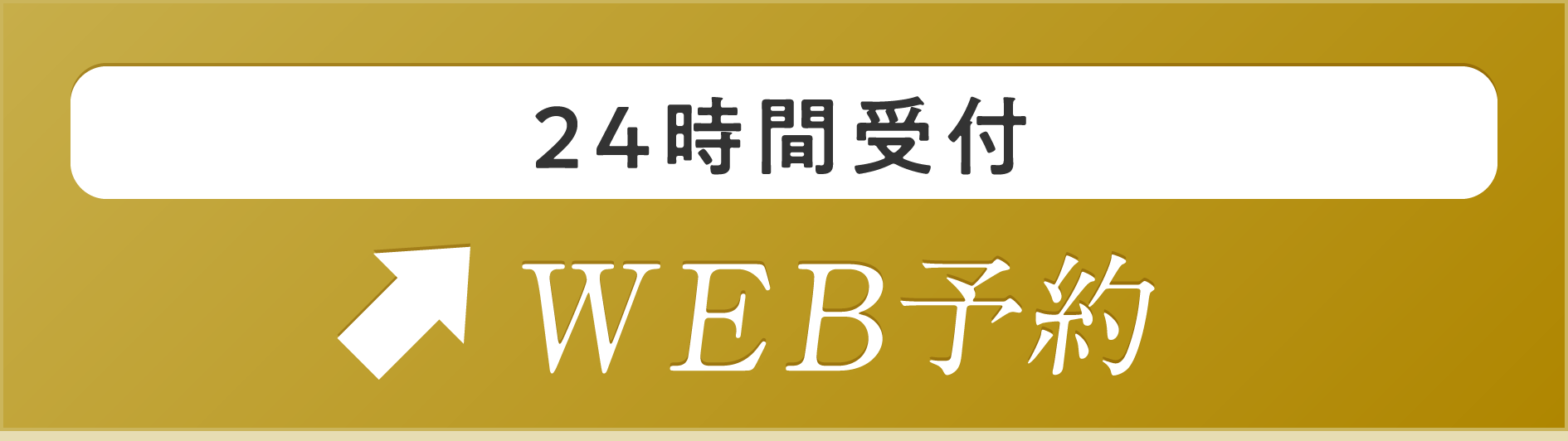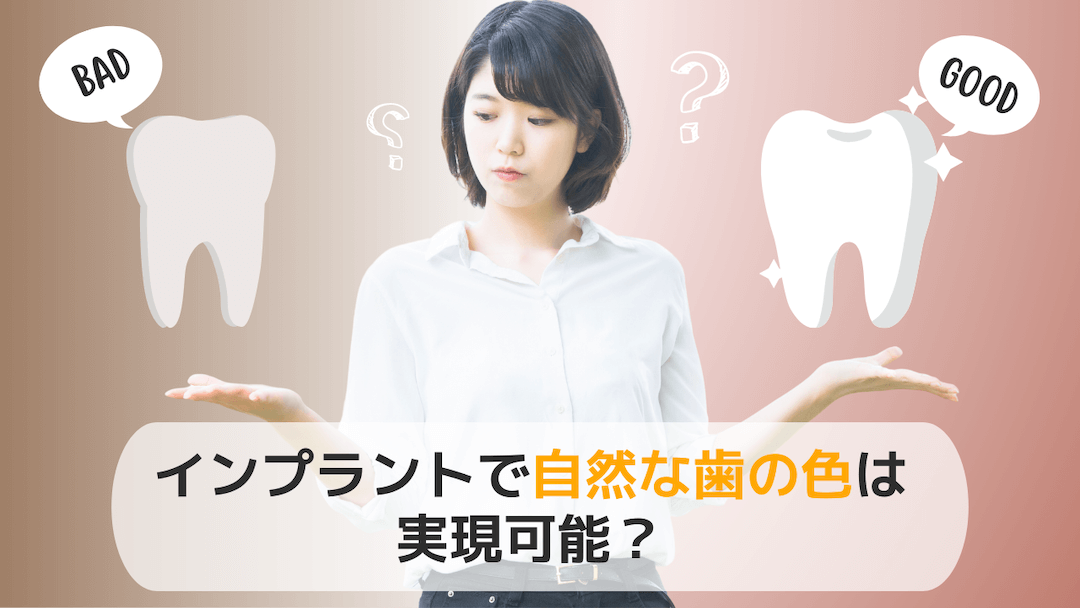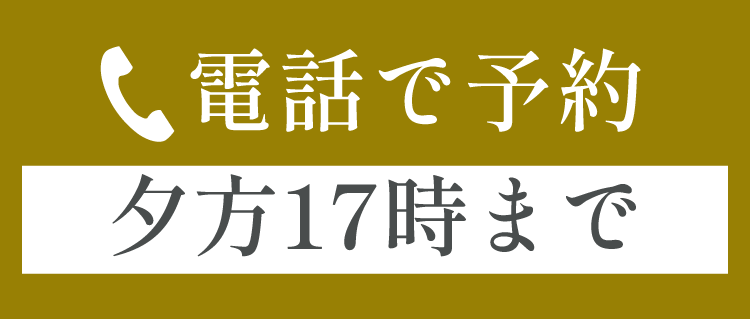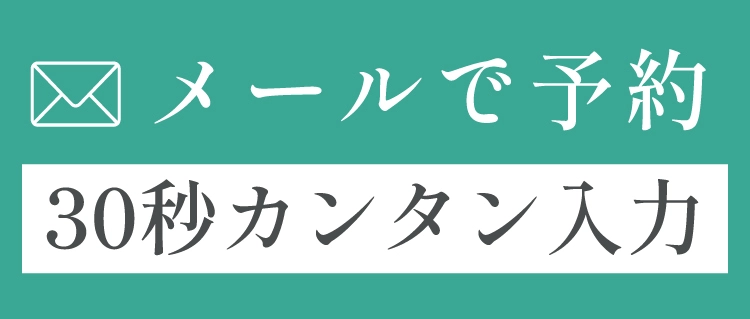インプラントとブリッジは、いずれも失った歯を補うための代表的な治療法です。
「どちらを選ぶべきか」「費用や見た目、寿命にどのような違いがあるのか」など、治療を検討している方にとっては気になる点が多いでしょう。特に、歯を失った位置や本数、残っている歯の状態によって適した方法は変わります。
また、見た目の自然さや噛み心地、他の歯への負担、将来的なメンテナンス性など、比較すべき要素は多岐にわたります。誤った選択をすると、数年後に再治療が必要になったり、健康な歯を失うリスクが高まることもあるため、正しい知識に基づいた判断が欠かせません。
この記事では、インプラントとブリッジの基本的な仕組みから、それぞれのメリット・デメリット、費用相場や寿命の違いまで、大阪でインプラント治療を専門的に行う帝塚山スマイルデザインクリニック、院長の岩下が専門的な視点で詳しく解説します。
目次
インプラントとブリッジの違いと基本概要
歯を失ったときに選ばれる治療法として、インプラントとブリッジはいずれも広く普及しています。
どちらも欠損部分を補い、噛む機能や見た目を回復させることができますが、その仕組みや歯への影響、治療期間、費用などには大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの治療法の基本的な特徴と適応の目安を押さえておきましょう。
インプラントとは(人工歯根を用いた治療)
インプラントは、歯を失った部分の顎骨に人工歯根(主にチタン製)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。
周囲の歯に依存せず単独で機能するため、噛み心地や見た目が天然歯に近いという特徴があります。
骨としっかり結合することで高い安定性を得られ、適切なメンテナンスを行えば10年以上の長期使用も可能です。
ブリッジとは(隣の歯を削って橋をかける治療)
ブリッジは、欠損した部分の両隣の歯を支台として削り、連結した人工歯を橋のように装着する治療法です。
外科手術が不要で比較的短期間で治療でき、保険診療の範囲でも対応可能なケースが多いのが利点です。
一方で、健康な歯を削る必要があるため、支台歯の寿命が短くなるリスクも伴います。
適応の目安と一般的な使い分け
インプラントは、支台歯に負担をかけたくない方や、残存歯を長く保ちたい方に向いています。
ブリッジは、外科手術を避けたい場合や、骨量が不足している場合などに選ばれることが多いです。
どちらが適しているかは、口腔内の状態、全身の健康状態、ライフスタイル、費用面などを総合的に考慮して判断します。
インプラントブリッジ
インプラントブリッジとは、複数の歯を失った場合に、複数本のインプラントを支台として連結した人工歯を装着する治療法です。
すべての欠損部位にインプラントを埋め込む必要がないため、費用や手術の負担を軽減できる場合があります。
また、固定式のため装着感や噛み心地は天然歯に近く、見た目も自然に仕上げやすいという特徴があります。
インプラントブリッジとは何か
通常のブリッジは隣在歯を削って支台にしますが、インプラントブリッジでは人工歯根を支台として使用します。
例えば、3本分の欠損を2本のインプラントで支える設計が一般的です。
この方法により、治療本数や外科的侵襲を最小限に抑えることができます。
使われるケースの一例(複数歯欠損時など)
- 奥歯を2〜3本連続して失ったケース
- 部分的に骨量が足りず、すべての部位にインプラントが埋入できない場合
- 前歯部の審美性と奥歯部の咬合力を両立させたいケース
ただし、骨量や噛み合わせの状態によっては適応にならないこともあるため、精密な診査が欠かせません。
インプラントとブリッジの比較
インプラントとブリッジは、いずれも欠損部分を補う固定式の治療法ですが、その仕組みや歯への影響、治療期間、費用などに明確な違いがあります。
どちらが適しているかは、単純な優劣ではなく「患者さんの口腔環境やライフスタイルにどちらが合うか」によって変わります。
ここからは、重要な比較ポイントごとに詳しく見ていきましょう。
歯への影響(支台歯削合の有無)
インプラントは、欠損部分の顎骨に人工歯根を直接埋め込むため、隣接する健康な歯を削る必要がありません。
これは「支台歯削合が不要」という大きなメリットであり、残っている歯の寿命を延ばすことにもつながります。特に、将来的に他の歯を失うリスクを抑えたい場合や、健康な歯質を極力温存したい場合に有利です。
一方、ブリッジは欠損部の両隣の歯を支台として利用するため、支台歯の形態修正(削合)が必須です。
たとえ健康な歯であっても大きく削る必要があり、その結果、支台歯が虫歯や歯髄炎になりやすくなったり、将来的に根管治療や抜歯に至るリスクが高まります。
また、削った歯は元に戻すことができないため、この点は治療選択時に十分な理解と検討が必要です。
耐久性と清掃性の違い
インプラントは、顎骨と直接結合して力を支えるため、適切な設計とメンテナンスが行われれば10年以上、場合によっては20年以上の使用も期待できます。
ただし、清掃が不十分だとインプラント周囲炎を発症し、骨が吸収されて脱落に至ることもあるため、日々のホームケアと定期的なプロフェッショナルケアが欠かせません。
ブリッジは、適切な設計と管理がされていれば7〜10年程度の耐用が一般的です。
しかし、連結部や支台歯との境目に食べかすやプラークが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。特に、支台歯の清掃は通常の歯ブラシだけでは不十分で、デンタルフロスや歯間ブラシなど専用の清掃器具を使う必要があります。
耐久性を高めるには、設計段階で清掃性を確保することと、患者さん自身のセルフケア習慣の定着が重要です。
審美性と違和感
インプラントは、1本ずつ独立して設計できるため、天然歯とほぼ同じ形態や色調を再現しやすい治療法です。
歯肉との境目も自然に仕上げやすく、口を大きく開けたときや笑ったときでも人工物だと気づかれにくいのが特徴です。
また、噛んだときの感覚も天然歯に近く、装着後の違和感は比較的少ないといわれています。
一方、ブリッジは連結構造であるため、特に前歯部では色調や形態の再現性が課題となることがあります。
また、ポンティック(欠損部を補う人工歯)が歯肉と密着しない設計の場合、空間に食べかすが溜まりやすく、舌触りや発音に違和感を覚える方もいます。
見た目を重視する場合は、材質や形態の調整に加え、技工士との密な連携が重要です。
通院回数・治療期間
インプラントは外科手術を伴うため、治療期間が比較的長くなります。
一般的には、埋入手術から人工歯の装着まで3〜6か月ほどかかりますが、骨造成や複雑な補綴設計が必要な場合は1年近くかかることもあります。
また、手術前の精密検査や治癒期間中の経過観察など、通院回数も複数回にわたります。
ブリッジは外科処置が不要なため、比較的短期間で治療を終えることが可能です。
支台歯の形成から型取り、装着までおよそ2〜3回の通院で完了するケースもあります。
ただし、支台歯に問題がある場合や補綴設計が複雑な場合は、追加の治療や通院が必要になることがあります。
インプラントとブリッジの費用相場と内訳
インプラントとブリッジは、治療方法だけでなく費用の構造や総額にも大きな差があります。
特にインプラントは自費診療が基本となるため、治療本数や使用する材料、骨造成の有無などによって費用が大きく変動します。
一方、ブリッジは保険適用となる場合も多く、自己負担を抑えられるケースがありますが、保険適用の範囲内では材質や設計に制限があります。
ここでは、両者の費用相場とその内訳について詳しく解説します。
一般的な費用帯の目安
インプラントの費用は、1本あたりおおよそ30万〜50万円が相場です。
この金額には、人工歯根の埋入手術費用、アバットメント(人工歯根と被せ物をつなぐ部品)、上部構造(被せ物)の費用が含まれるのが一般的です。
ただし、骨造成やサージカルガイドの使用、特注の上部構造などが加わる場合、総額が60万円を超えることも珍しくありません。
ブリッジの費用は、保険適用の場合であれば3割負担で1本あたり数千円〜1万円台で治療できます。
一方、自費診療でセラミックやジルコニアを使用する場合は、3本連結で15万〜30万円程度が相場です。
材質や設計によって見た目や耐久性が大きく変わるため、見た目や長期的な安定性を重視する方は自費ブリッジを選ぶこともあります。
インプラントブリッジの費用パターン
インプラントブリッジは、すべての欠損部にインプラントを埋めるのではなく、必要な本数だけインプラントを入れて人工歯を連結する方法です。
例えば3本分の欠損を2本のインプラントで支える場合、費用は「インプラント2本分+ポンティック(連結歯)1本分」という計算になります。
一般的な相場では、インプラント1本あたり30万〜50万円程度に加え、ポンティック部分は1本あたり10万〜15万円程度が目安です。
そのため、3本分を2本のインプラントで支える場合、総額は70万〜110万円程度になることが多いです。
また、使用する被せ物の材質(ジルコニア・セラミックなど)や設計の複雑さによっても費用は変動します。
骨造成やガイドサージェリーを併用する場合はさらに数万〜十数万円の追加費用が発生するため、治療前に見積もりをしっかり確認することが大切です。
追加費用になりやすい項目
インプラントやインプラントブリッジの治療では、基本費用のほかに追加費用が発生することがあります。
代表的な項目としては以下のようなものがあります。
骨造成(GBRやサイナスリフトなど)
顎の骨量が不足している場合、インプラントを安定させるために骨を増やす手術を行います。費用は片顎で5万〜20万円程度が目安です。
サージカルガイド
手術の精度を高めるために使用する3Dプリント製の手術用ガイドで、3万〜10万円程度かかります。
仮歯・暫間補綴
治療中に見た目や噛み合わせを保つための仮の歯を作る場合、1本あたり5千〜1万円程度の費用が追加されることがあります。
静脈内鎮静法などの麻酔オプション
手術時の不安や痛みを軽減するための鎮静法で5万〜10万円程度が一般的です。
これらは患者さんの口腔状態や希望に応じて必要になるため、カウンセリングの段階でしっかりと説明を受け、総額を把握しておくことが重要です。
インプラントの本数と配置の考え方
インプラント治療では、欠損部の本数とその配置によって、治療設計や必要なインプラント本数が大きく変わります。
必ずしも失った歯の本数分だけインプラントを埋入する必要はなく、連結構造を活用して本数を減らすことも可能です。
一方で、支えるインプラントの本数が少なすぎると噛む力の分散が不十分になり、破損や脱落のリスクが高まります。
また、前歯部と奥歯部では審美性や咬合力の要求が異なるため、配置の考え方にも違いがあります。
ここでは、安全性と長期安定性を考慮した本数と配置の基本的な考え方を解説します。
1本支台で複数歯はなぜ推奨されにくいか
インプラント1本で複数の人工歯を支える設計は、咬合力の集中による負担が大きく、長期的な安定性に欠ける傾向があります。
特に奥歯のように噛む力が強くかかる部位では、1本のインプラントに過大な力が加わり、インプラント体や上部構造の破損、ネジの緩みなどのトラブルが発生しやすくなります。
さらに、1本支台では咬合時の揺れや歪みが生じやすく、周囲の骨にストレスが集中します。
これにより骨吸収が進み、インプラントの寿命が短くなるリスクがあります。
そのため、1本支台で複数歯を支える設計は特別な理由がない限り推奨されず、複数歯欠損の場合は2本以上の支台インプラントを配置するのが一般的です。
2本支台で複数歯回復の一般的パターン
複数歯を失った場合、2本のインプラントを支台として、その間にポンティック(連結された人工歯)を配置する方法が広く用いられます。
例えば3本欠損の場合、両端にインプラントを埋入し中央をポンティックで補う「インプラントブリッジ」が代表的な設計です。
この方法は、全ての欠損部にインプラントを埋めるよりも手術回数・費用を抑えられる一方で、咬合力をバランスよく分散できるため長期安定性が高いのが特徴です。
また、骨量が不足している部位や解剖学的制限(上顎洞や神経管など)がある部位を避けてインプラントを配置できるという利点もあります。
ただし、ポンティック部は清掃性の確保が課題となるため、設計時に適切なスペースを設け、患者さん自身が日常的にケアしやすい形態にすることが重要です。
前歯・奥歯での設計上の違い
前歯部は審美性が重視されるため、インプラントの位置や角度、歯肉の形態を細かく調整する必要があります。
1本あたりにかかる咬合力は比較的弱いため、設計上は審美的な調和や発音時の違和感を抑えることが優先されます。
また、歯肉との境目が自然に見えるよう、上部構造の材質や色調選びにも配慮が必要です。
一方、奥歯部は咬合力が非常に強くかかるため、耐久性と力の分散が最優先となります。
インプラントの直径や長さを十分に確保し、場合によっては支台インプラントを増やす設計を行います。
また、奥歯部では見た目よりも清掃性と機能性を優先し、咀嚼効率を高める形態に仕上げることが重要です。
入れ歯との比較
歯を失った際の治療法としては、インプラントやブリッジだけでなく、取り外し式の入れ歯(義歯)も広く選択されています。
入れ歯は外科手術が不要で費用も比較的抑えられる一方、装着感や咀嚼力、見た目などの面で固定式の治療と異なる特徴があります。
ここでは、インプラントやブリッジと入れ歯を比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。
装着感・食事の満足度
インプラントやブリッジは顎骨に固定されているため、装着感が自然で違和感が少なく、咀嚼力も天然歯に近い水準まで回復しやすいのが特徴です。
硬い食べ物や繊維質の多い食材でもしっかり噛むことができ、食事中に外れる心配もありません。
一方、入れ歯は取り外し式で、歯ぐきや残存歯に負担をかけながら支える構造のため、噛む力は天然歯やインプラントに比べて弱くなります。
特に総入れ歯の場合は、安定感を確保するために吸着や義歯用接着剤に頼ることがあり、食事中にずれたり外れたりする不安を感じる方もいます。
また、入れ歯の厚みや構造によって発音がしにくくなることや、装着初期に違和感を覚えるケースも少なくありません。
インプラント・ブリッジは、いずれも口の中に固定された状態で使うため、装着中の清掃は天然歯と同じように歯ブラシで行います。
ただし、ブリッジやインプラントブリッジは連結構造のため、人工歯の下や支台部分に食べかすやプラークが溜まりやすく、通常の歯ブラシだけでは不十分です。
スーパーフロスや歯間ブラシ、専用の清掃器具を併用して、隙間や境目の汚れを除去することが長期安定のカギとなります。
入れ歯は、毎日取り外して洗浄できる点で清掃しやすい一方、義歯床と歯ぐきの間に食べかすが入り込みやすく、放置すると口臭や義歯性口内炎の原因になります。
また、残存歯を支えにする部分入れ歯では、金属のバネ(クラスプ)周囲に汚れが付着しやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
清掃習慣を守ることはもちろん、定期的に歯科医院で義歯や口腔内のチェックを受けることが不可欠です。
費用と保険適用の有無
インプラントは、基本的に自由診療であり保険は適用されません。
1本あたり30万〜50万円程度が相場で、材料や設計、追加処置によってはさらに高額になります。
また、インプラントブリッジも同様に自費診療となり、本数や構造によって総額が大きく変動します。
ブリッジは、条件を満たせば保険診療での治療が可能です。
保険適用の場合は、素材が銀合金や硬質レジンに限られ、見た目や耐久性に制限があります。
自費ブリッジではセラミックやジルコニアなどの審美性・耐久性に優れた素材が選べますが、費用は3本連結で15万〜30万円程度が目安です。
入れ歯は、ほとんどの場合で保険適用が可能で、自己負担を抑えられます。
ただし、保険義歯は素材や設計の自由度が低く、快適性や見た目にこだわる場合は自費の金属床義歯やノンクラスプデンチャーなどを選ぶ必要があり、その場合は10万〜30万円程度の費用がかかります。
治療の流れ・期間・通院回数
インプラントとブリッジは、治療の手順や必要な通院回数、全体の期間が大きく異なります。
インプラントは外科手術を伴うため、事前の精密検査や治癒期間を含めると数か月〜1年ほどかかることもあります。
一方、ブリッジは外科処置が不要で、支台歯の状態に問題がなければ2〜3回の通院で装着まで完了するケースもあります。
治療期間や回数は口腔内の状態や治療計画によって変わるため、初診の段階で全体の流れを把握しておくことが重要です。
検査・診断
治療を始める前には、現在の口腔内の状態を正確に把握するための検査と診断が行われます。
インプラントの場合は、レントゲン撮影やCT撮影で顎骨の高さ・厚み・骨質を確認し、神経や血管の位置も詳細にチェックします。
これにより、インプラントの埋入位置や角度、必要な本数を決定します。骨量が不足している場合には、骨造成の必要性もこの段階で判断します。
ブリッジの場合は、支台歯となる隣接歯の状態を確認します。虫歯や歯周病があれば、事前に治療して健康な状態に整えてから支台歯形成を行います。
また、噛み合わせや歯列全体のバランスも評価し、ブリッジの設計に反映させます。
いずれの場合も、患者さんの希望や生活スタイル、治療にかけられる期間や費用を考慮したうえで、複数の治療プランを提示するのが理想です。
手術・治癒・上部構造装着
インプラントの場合、まず局所麻酔下で顎骨に人工歯根を埋入する一次手術を行います。
手術時間は本数や部位によって異なりますが、1本であればおおよそ30分〜1時間程度です。
埋入後は骨とインプラントが結合する「オッセオインテグレーション」という期間が必要で、通常は2〜6か月ほどかかります。
この間に仮歯を装着して見た目や噛み合わせを維持する場合もあります。
結合が確認できたら、アバットメント(連結部品)を装着し、その上に被せ物を取り付けて治療が完了します。
ブリッジの場合は、支台歯を削って形を整えたあと、型取りを行います。
その後、歯科技工士が作製したブリッジを口腔内に装着し、咬み合わせや見た目を調整します。
治療全体は2〜3週間程度で終わることが多く、仮歯を使って経過を見る場合でも1か月以内に完了するケースがほとんどです。
通院回数・期間の目安
インプラントは、検査・診断から治療完了までにおよそ3〜6か月が一般的です。
骨造成が必要な場合や、上顎の骨質が柔らかい場合には治癒期間を長めに取るため、1年近くかかることもあります。
通院回数は、検査・カウンセリング、手術、経過観察、上部構造の装着、メンテナンスなどを含めて5〜10回程度が目安です。
ブリッジは、支台歯に問題がなければ2〜3回の通院で装着可能です。
初回で支台歯形成と型取りを行い、2回目で装着する流れが一般的です。
ただし、支台歯の治療や仮歯での経過観察が必要な場合には、期間や回数が増えることがあります。
リスク・注意点
インプラントやブリッジは、適切に治療が行われれば長期的に機能しますが、いずれも特有のリスクや注意点があります。
これらを理解せずに治療を選択すると、数年後に再治療が必要になったり、残っている歯や顎骨に負担がかかることがあります。
ここでは、インプラントとブリッジそれぞれに共通するものと、それぞれに特有のリスクについて解説します。
手術関連のリスク
インプラント治療では外科手術を伴うため、特有のリスクが存在します。
代表的なものとしては、手術部位の腫れや痛み、出血、感染症の発症があります。
通常は数日〜1週間程度で軽快しますが、免疫力が低下している場合や清掃が不十分な場合には症状が長引くこともあります。
また、顎骨内の神経や血管、上顎洞などの解剖学的構造を損傷するリスクもあります。
これらは術前のCT検査と適切な手術計画で大部分を回避できますが、術者の経験や技術にも影響されます。
一方、ブリッジの場合は外科処置は不要ですが、支台歯を大きく削ることにより歯髄炎や歯の破折などのリスクが生じます。
特に神経に近い部分まで削る必要がある場合、治療後に歯がしみる・痛むといった症状が出ることもあります。
インプラント周囲炎と予防
インプラント周囲炎は、インプラントの周囲に炎症が起こり、歯肉や骨が破壊されていく病気です。
原因の多くは、清掃不良によるプラークの蓄積や、噛み合わせによる過剰な負荷です。
放置すると顎骨が吸収され、インプラントが動揺・脱落することもあります。
予防のためには、天然歯と同様に毎日の歯磨きに加え、歯間ブラシやスーパーフロスなど専用の清掃器具を使って汚れを徹底的に除去することが重要です。
また、3〜6か月ごとの定期検診で歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを受け、咬合状態やインプラント周囲組織の健康状態をチェックすることも欠かせません。
ブリッジの場合も、支台歯の周囲にプラークが溜まると虫歯や歯周病のリスクが高まります。
特に連結構造の下部や支台歯と人工歯の境目は汚れが残りやすいため、意識的な清掃が必要です。
ブリッジ特有のリスク
ブリッジは、欠損部を補うために両隣の歯を支台として削り、連結した人工歯を装着する構造です。
このため、支台歯に大きな負担がかかりやすく、長期的には歯根の破折や歯周病の進行を招くことがあります。
また、支台歯の周囲は清掃が難しく、特にポンティック(人工歯の下)部分に食べかすやプラークが蓄積しやすい傾向があります。
これを放置すると、支台歯が虫歯になったり、歯肉炎・歯周炎を発症しやすくなります。
さらに、一度削った歯は元の状態には戻せないため、支台歯の寿命が短くなれば、ブリッジ全体の再製作や、場合によってはインプラントや入れ歯への移行が必要になることもあります。
これらのリスクを軽減するためには、設計段階で清掃性を確保し、日常のセルフケアと定期的なメンテナンスを徹底することが重要です。
メンテナンス方法
インプラントやブリッジは、治療が完了した後も定期的なメンテナンスが欠かせません。
適切な清掃や定期検診を怠ると、インプラント周囲炎や支台歯の虫歯・歯周病などのトラブルが発生し、再治療が必要になることがあります。
特に固定式の補綴装置は一見きれいに見えても、見えない部分に汚れが蓄積しやすいため、セルフケアとプロケアの両方を組み合わせて管理することが重要です。
清掃器具の選び方
インプラントやブリッジの清掃には、通常の歯ブラシだけでなく、補助的な清掃器具を組み合わせることが効果的です。
インプラントやブリッジの支台部分やポンティック下は、歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが残りやすい部位です。
代表的な清掃器具には以下のようなものがあります。
- スーパーフロス:先端が硬く加工されており、ブリッジの下やインプラントの周囲に通しやすい特別なフロス。
- 歯間ブラシ:支台歯やインプラントの隙間に挿入し、側面の汚れを除去できる。金属ワイヤーが歯面を傷つけないよう、サイズ選びが重要。
- タフトブラシ:小さなヘッドで、奥まった部分や歯の裏側の清掃に適している。
患者さんによって口腔内の形態や補綴装置の設計は異なるため、歯科医院で自分に合った清掃器具と使い方を指導してもらうことが、長期的な予後に直結します。
定期検診の重要性
インプラントやブリッジを長持ちさせるためには、3〜6か月ごとの定期検診が不可欠です。
見た目には問題がなくても、内部や周囲の組織にトラブルが進行している場合があり、早期に発見することで大きな治療介入を避けられます。
定期検診では、以下のようなチェックや処置が行われます。
- 噛み合わせの確認と調整
- 補綴装置の固定状態や破損の有無の確認
- インプラント周囲や支台歯の歯周ポケット測定
- 専用器具によるクリーニングとバイオフィルム除去
- 清掃方法の再指導
これらを継続的に行うことで、インプラント周囲炎や二次う蝕などのリスクを最小限に抑えることができます。
また、生活習慣や全身状態の変化に応じて、清掃方法やメンテナンス間隔を見直すことも大切です。
当院の治療方針
帝塚山スマイルデザインクリニックでは、患者さん一人ひとりの口腔環境やライフスタイルに合わせ、長期的に安定する治療を重視しています。
特に、治療後も健康な歯や骨を守り続けられるよう、過度な削合や無理な設計は行いません。
また、治療の精度と仕上がりを高めるため、歯科技工士や歯科衛生士と密に連携し、審美性・機能性・清掃性を兼ね備えた補綴物を提供しています。
カウンセリングでは治療のメリットだけでなくリスクや代替案も丁寧に説明し、患者さんが納得した上で治療を進めることを大切にしています。
自分に合った治療法を選び、長く快適な口元を維持するために
インプラントとブリッジは、どちらも歯を失った部分を補う有効な方法ですが、それぞれに仕組み・費用・耐久性・メンテナンス性といった特徴があります。
インプラントは周囲の歯を守りつつ、天然歯に近い機能と見た目を回復できる一方で、外科手術や費用面のハードルがあります。
ブリッジは短期間で治療でき、保険適用も受けやすいものの、支台歯への負担や長期耐久性に注意が必要です。
当院では、患者さんの口腔内や生活スタイル、将来の健康まで考慮した治療計画をご提案しています。
「自分にとってどちらが最適か分からない」という段階からでも構いません。
まずは一度ご相談いただき、現在の状態やご希望に合わせた最適な選択肢を一緒に検討しましょう。
正しい知識と適切なメンテナンスを組み合わせることで、長く快適な口元を維持することが可能です。
【執筆・監修者】

帝塚山Smile Design Clinic(スマイルデザインクリニック)
院長:岩下太一(歯学博士)
ITI日本支部公認インプラントスペシャリスト認定医
オステムインプラントインストラクター 講師
日本審美歯科学会 認定医
他、所属学会、認定資格多数
充実した無料カウンセリング

初回費用は一切かかりません。安心してご相談ください。
当院では患者様に安心してインプラント治療を受けて頂くために、無料カウンセリングを充実させております。お口の中のお写真やレントゲン写真、場合によってはインプラントの骨を確認するためのCT撮影も無料で行います。もちろん、初回なので一切費用はかかりません。患者様に今のお口の状態を知って頂き、納得してインプラント治療を受けて頂くことが私たちの喜びです。
ITIインプラントスペシャリスト認定医

~ 世界レベルのインプラント治療をあなたへ ~
帝塚山スマイルデザインクリニックの院長はインプラント治療を他の歯科医師に教えるインストラクターの指導的立場として歯科界に貢献しております。また世界的に有名なインプラント学術団体のITI(International Team for Implantology)の日本支部公認インプラントスペシャリストの認定医でもあります。他院で難しいと言われたインプラント治療でも当院では十分に対応できる技術があります。