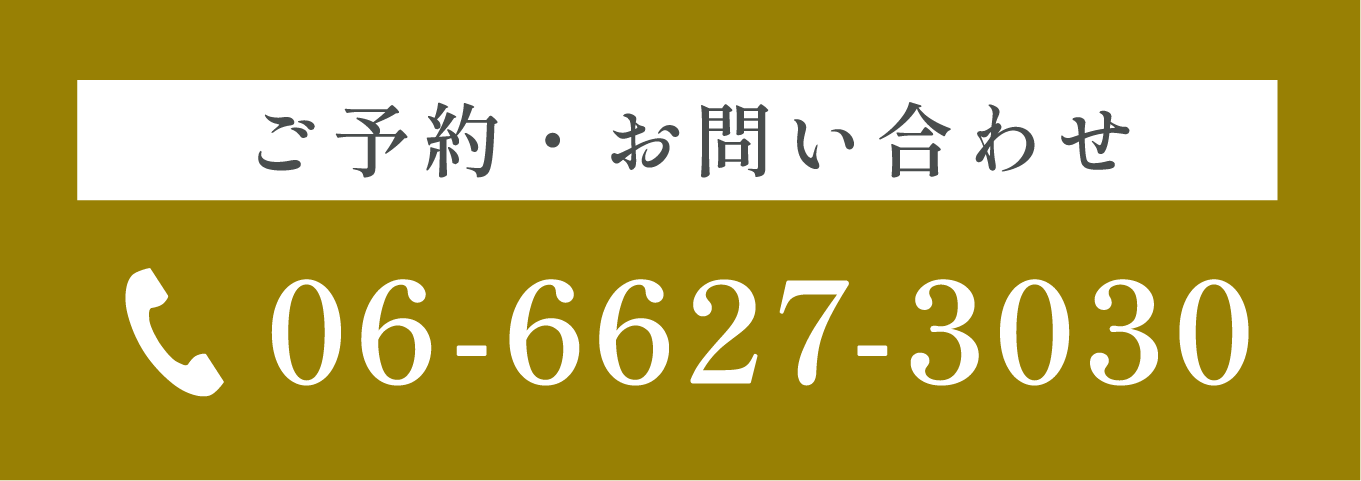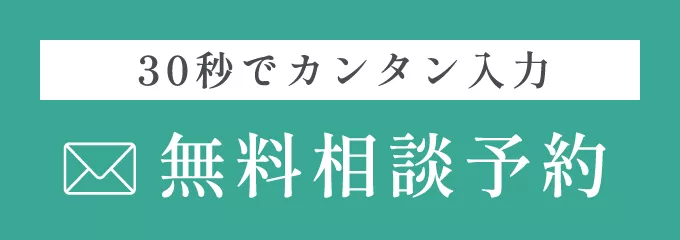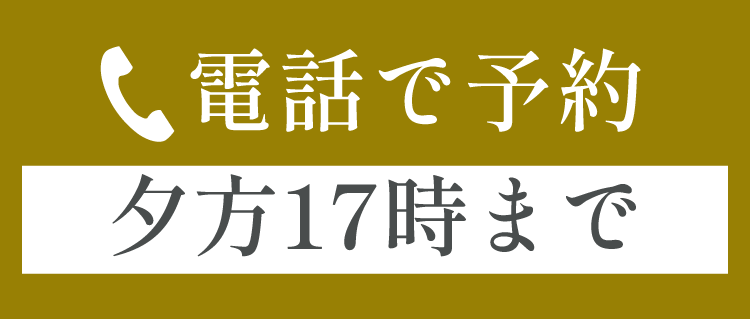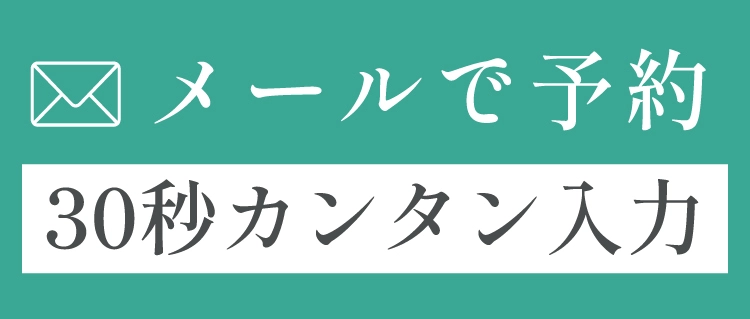前歯インプラントの10年後|見た目・機能・長期安定性を専門医が解説
前歯のインプラントに関心を持たれる方にとって、もっとも大きな不安は「10年後の見た目や使い心地がどうなっているのか」という点ではないでしょうか。奥歯と異なり、前歯は常に人の目に触れるため、色の調和や歯ぐきのラインといった審美性が求められます。また、発音や噛み心地といった機能面も、日常生活に直結する要素です。加えて、年月の経過とともに骨や歯ぐきが変化しやすく、 …

ジルコニアインプラントのデメリットとは?|チタンとの違いと費用・寿命を専門医が解説
「体に優しい」「見た目が自然」といった理由から、金属を使わないジルコニアインプラントに関心を持つ方は近年増えています。 そもそも主にインプラントの素材として使用されるチタンは、金属アレルギーを起こしにくい素材として知られていますが、それでも稀に金属アレルギーが出てしまう患者様がおられます。対してジルコニアインプラントは金属アレルギーのリスクがない素材として注 …
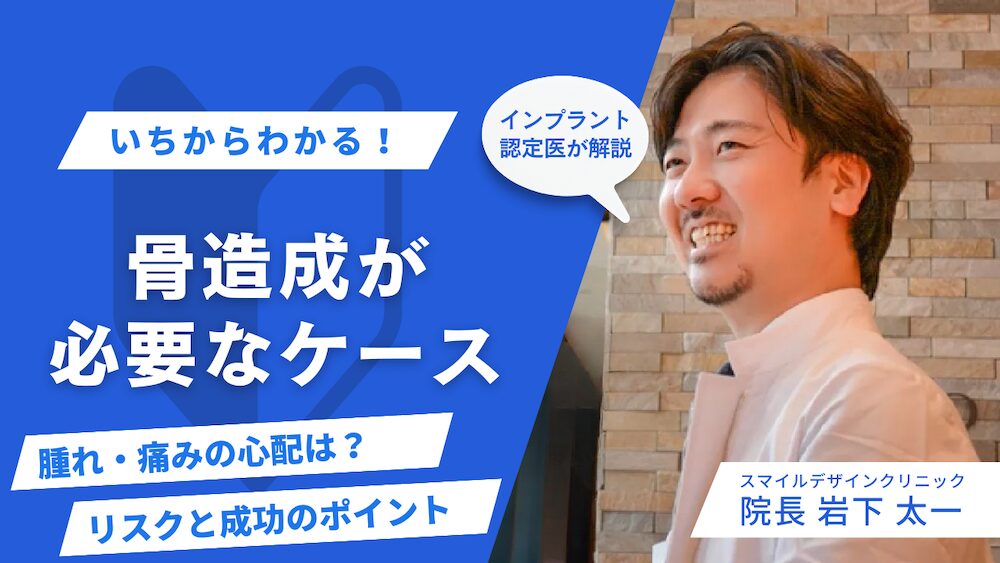
インプラントで骨造成が必要な場合とは|腫れ・痛み・リスクと成功のポイント
インプラント治療を検討している方の中には、「骨造成が必要と言われたけれど、痛みや腫れが不安」「そもそも骨造成とはどんな治療なのか」と疑問を抱かれる方も少なくありません。骨造成は、顎の骨が不足している場合に行われる手術であり、インプラントを安定して支えるために欠かせない工程となることがあります。 本記事では、骨造成の仕組みや必要となる理由、代表的な方法(GBR …
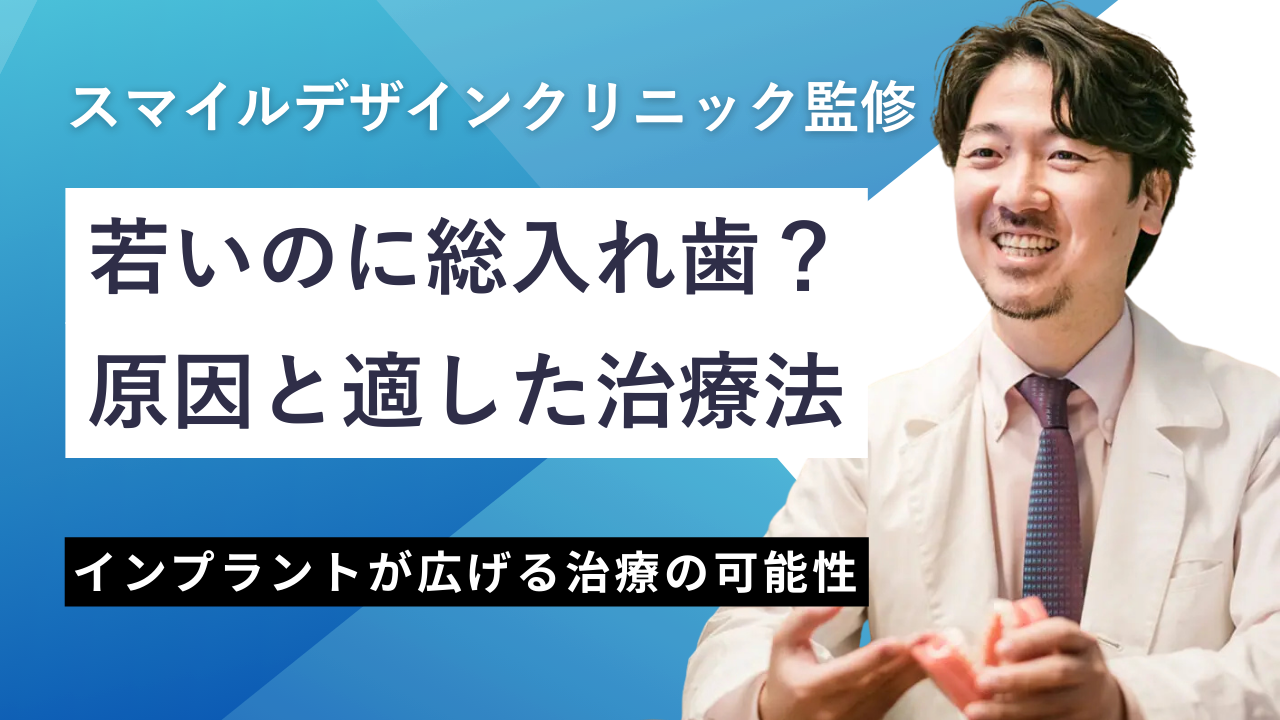
若いのに「総入れ歯」と言われたら?知っておきたい原因と治療法
「若いのに総入れ歯」と聞くと、大きなショックを受けたり、「恥ずかしいのではないか」と不安に感じてしまう方も少なくありません。けれども、実際には30代や40代、さらには50代といった比較的若い世代でも、総入れ歯が必要になるケースは決して珍しいことではないのです。 本記事では、なぜ若くして総入れ歯になるのかという原因や背景をわかりやすく解説するとともに、審美性や …
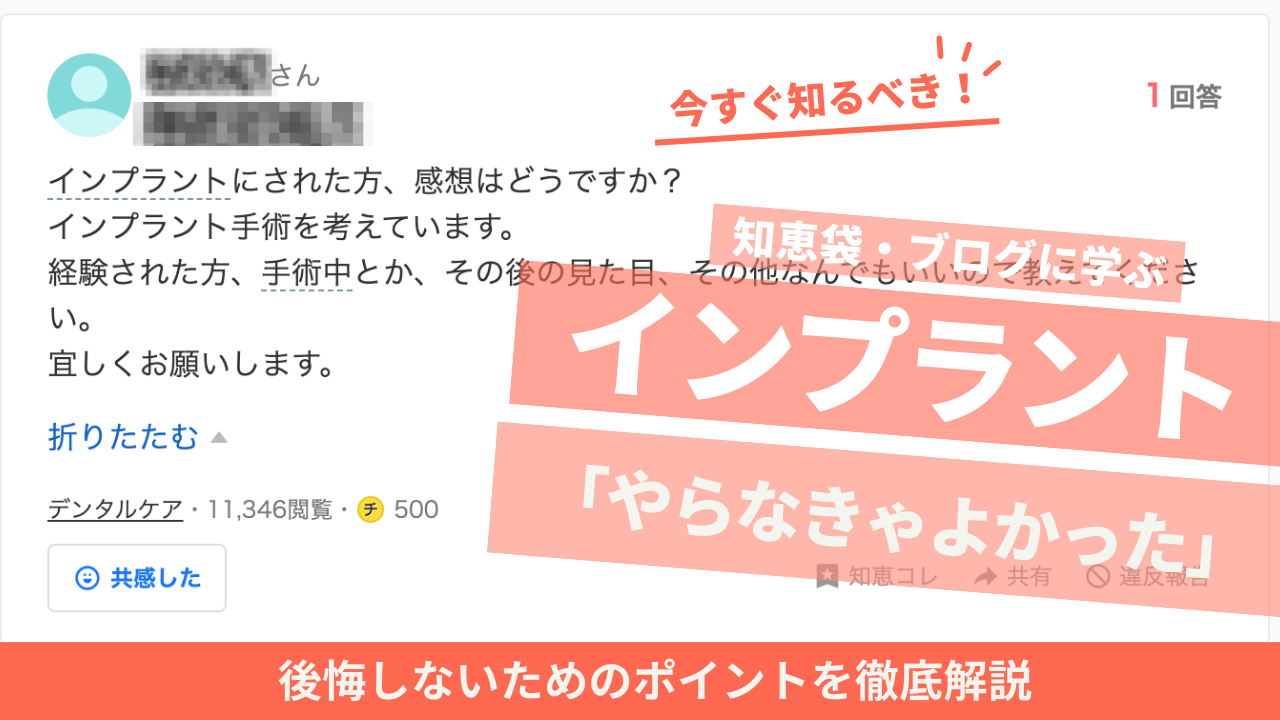
知恵袋・ブログに学ぶインプラントで「やらなきゃよかった」と後悔しないためのポイント
「インプラントをやらなきゃよかった」という言葉を、知恵袋やブログで目にしたことはありませんか。実際に検索では「インプラント やらなきゃよかった 知恵袋」「インプラント やらなきゃよかった ブログ」といったキーワードが多く見られ、体験談をもとにした“後悔の声”を探している方が少なくないことがわかります。 確かにインプラント治療は一生に関わる大きな選択であり、費 …