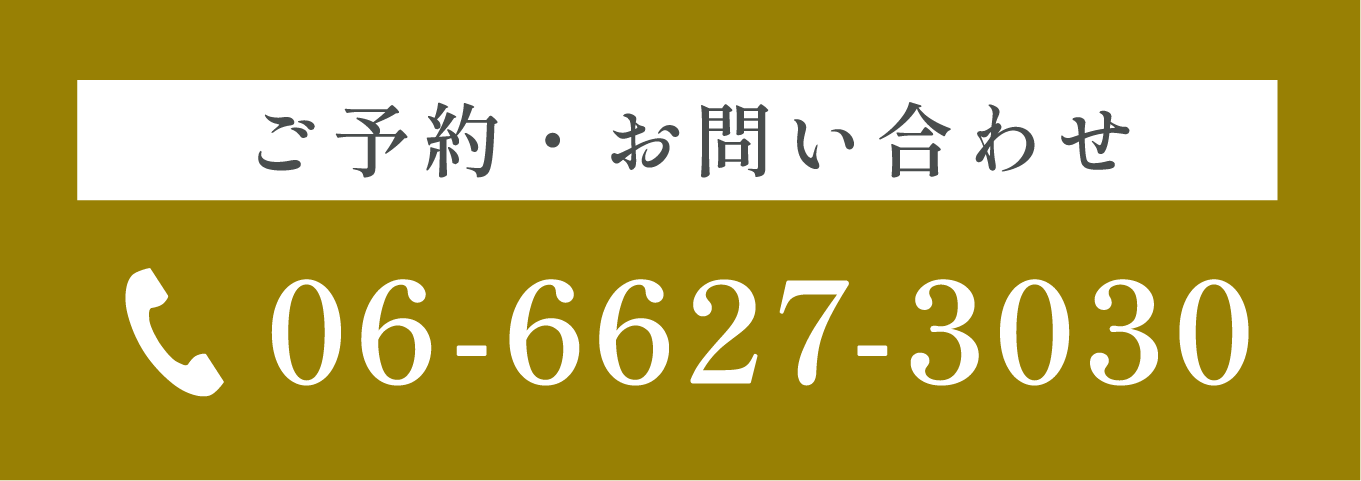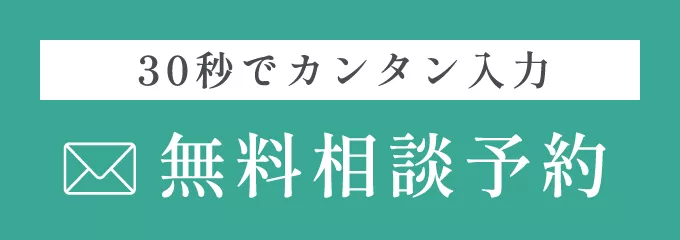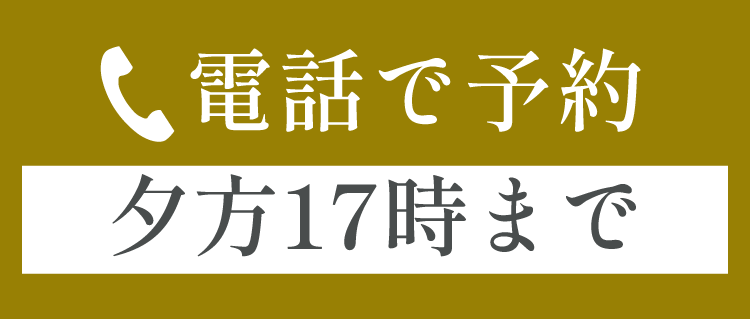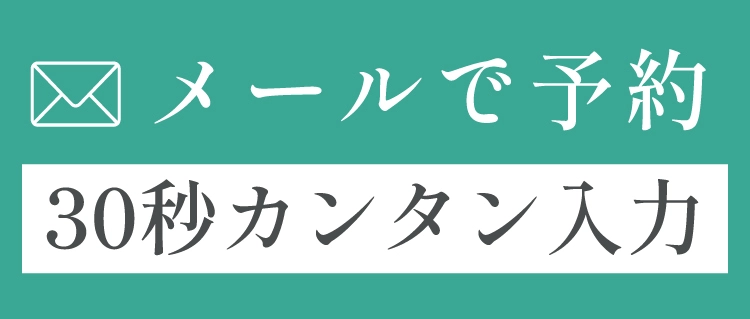インプラントは老後に悲惨?その原因と後悔しないための対策を歯科医が解説
インプラントは老後になると悲惨なことになる」そんな不安を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。確かに、インプラントは天然歯に近い噛み心地や見た目を再現できる一方で、加齢に伴う骨や歯茎の変化、全身疾患、介護や入院といった生活環境の影響を受けやすい面があります。 そのため、適切な設計や管理が行われないまま治療を受けると、将来的にトラブルや再治療につなが …

40代で入れ歯は恥ずかしい?心理・対策・自然に見える治療法まで解説
「40代で入れ歯なんて恥ずかしい…」歯を失った際の治療法として入れ歯を提案されても、年齢的な抵抗感や見た目への不安から、なかなか決断できない方は少なくありません。特に40代は、仕事や人間関係などで人と接する機会も多く、「口元が老けて見えるのでは」「話すときに入れ歯が気づかれるのでは」といった心配がつきまとうものです。 しかし、40代で歯を失うことは決して珍し …

ブリッジにするかインプラントにするか決められない方へ|後悔しない選び方と比較ポイント
「ブリッジにするか、インプラントにするか決められない…」失った歯を補う治療法として代表的なのが、この2つです。しかし、それぞれ見た目や噛み心地、治療の流れ、費用、寿命などに違いがあり、どちらを選ぶべきか迷う方は少なくありません。 選択を誤ると、数年後に再治療が必要になったり、健康な歯や骨に負担をかけてしまう可能性もあります。反対に、自分に合った方法を選べば、 …

インプラント前歯1本の費用相場と内訳|見た目・機能性も解説
前歯は、会話や笑顔の際にもっとも目に入りやすく、見た目の印象を大きく左右する歯です。さらに、発音や咬み切る動作にも関わるため、1本失うだけでも日常生活にさまざまな影響が出ます。 失った前歯を補う治療法の中でも、自然な見た目と噛み心地を両立できるのが「インプラント治療」です。周囲の歯を削らずに単独で機能を回復できる点から、多くの方が選択肢に挙げます。しかし、「 …

奥歯1本のインプラント費用相場と選び方|インプラント専門医が解説
奥歯は、食事の際に大きな力を受け止め、噛み砕く役割を担う非常に重要な歯です。そのため、奥歯を1本失ってしまうと、噛み合わせのバランスが崩れ、反対側の歯や顎関節に負担がかかるだけでなく、将来的に他の歯を失うリスクも高まります。 失った奥歯を補う代表的な治療法のひとつが「インプラント治療」です。自然な噛み心地や見た目の美しさ、周囲の歯への負担が少ないことから、多 …