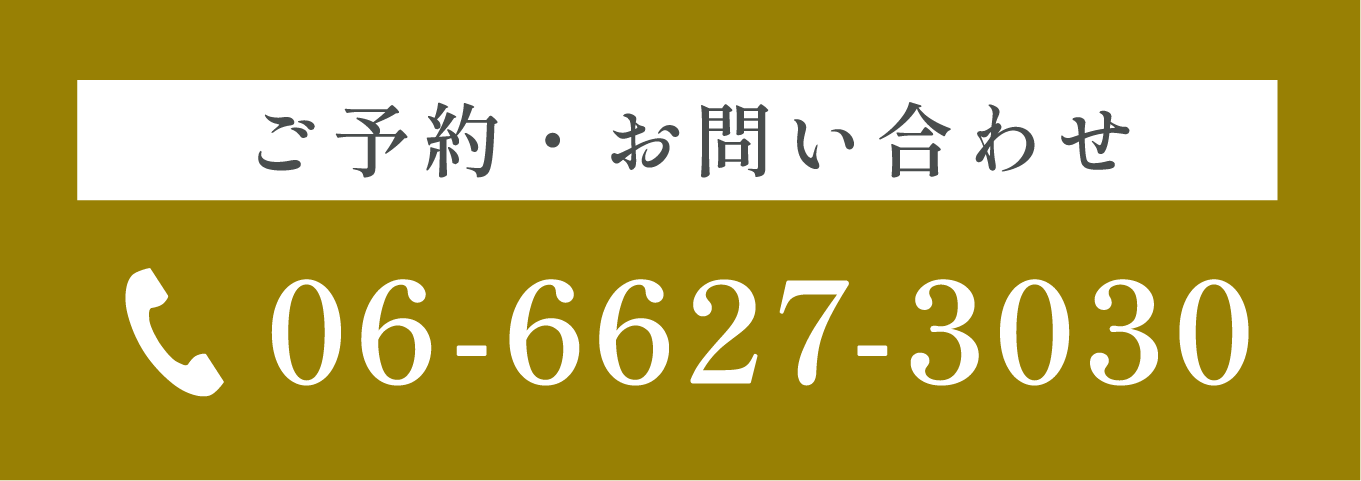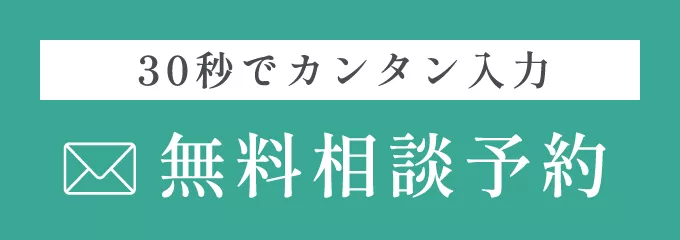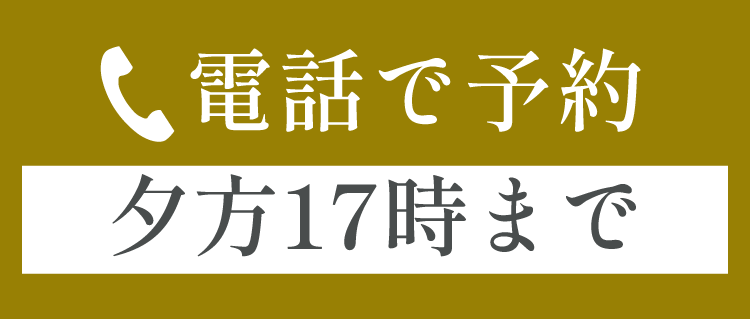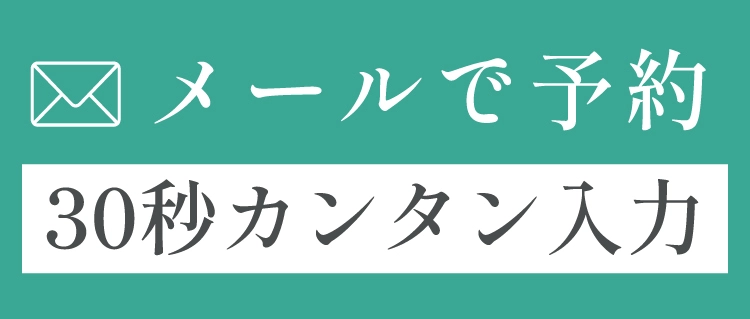インプラントとブリッジ、どっちがいい?違い・選び方・費用・寿命まで徹底解説
インプラントとブリッジは、いずれも失った歯を補うための代表的な治療法です。「どちらを選ぶべきか」「費用や見た目、寿命にどのような違いがあるのか」など、治療を検討している方にとっては気になる点が多いでしょう。特に、歯を失った位置や本数、残っている歯の状態によって適した方法は変わります。 また、見た目の自然さや噛み心地、他の歯への負担、将来的なメンテナンス性など …

インプラント治療と喫煙|タバコがやめられない場合のリスクと対策
インプラント治療は、失った歯を取り戻すための有効な方法ですが、その成功と長期的な安定性は日常の生活習慣にも左右されます。特に喫煙は、治療の成否を大きく左右する要因のひとつです。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素などの有害物質は、歯茎や骨の血流を悪化させ、傷の治りを遅らせるだけでなく、インプラントと骨の結合(オッセオインテグレーション)を妨げる原因となります …

インプラント3本連結はいくら?費用相場・内訳・費用を抑える方法
「インプラントを3本連結すると、いくらかかるのだろう…」そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。単独で3本のインプラントを入れる場合と、連結して入れる場合では、構造や費用の内訳が異なります。また、部位や素材、治療計画によっても総額は大きく変わります。 本記事では、大阪でインプラント治療を専門的に行う帝塚山スマイルデザインクリニック院長の岩下が、インプラント …

20代でインプラントを受けた体験談|大阪の歯科医が解説するメリット・注意点
「まだ20代なのに、インプラント治療を受けても大丈夫なのだろうか…」そう不安に思われる方も少なくありません。事故や虫歯、先天的な欠損などで若くして歯を失った場合、見た目や噛む機能だけでなく、将来の口腔環境にも影響します。 一方で、20代は骨や歯ぐきの状態が良く、インプラントが長期的に機能しやすい時期でもあります。しかし、メリットだけでなく、将来を見据えた注意 …

インプラントの種類とは?構造・素材・メーカー別にわかりやすく解説
インプラント治療に関心はあるものの、「どのような種類があるのかよくわからない」と感じる方も多くいらっしゃいます。実際、インプラントには構造・素材・形状・メーカーなど、さまざまな分類が存在し、患者さま一人ひとりの骨の状態やご希望によって、最適な種類が異なります。 また、近年では骨量が少ない方にも対応できるショートインプラントや、全顎的な治療を可能にする特殊な設 …