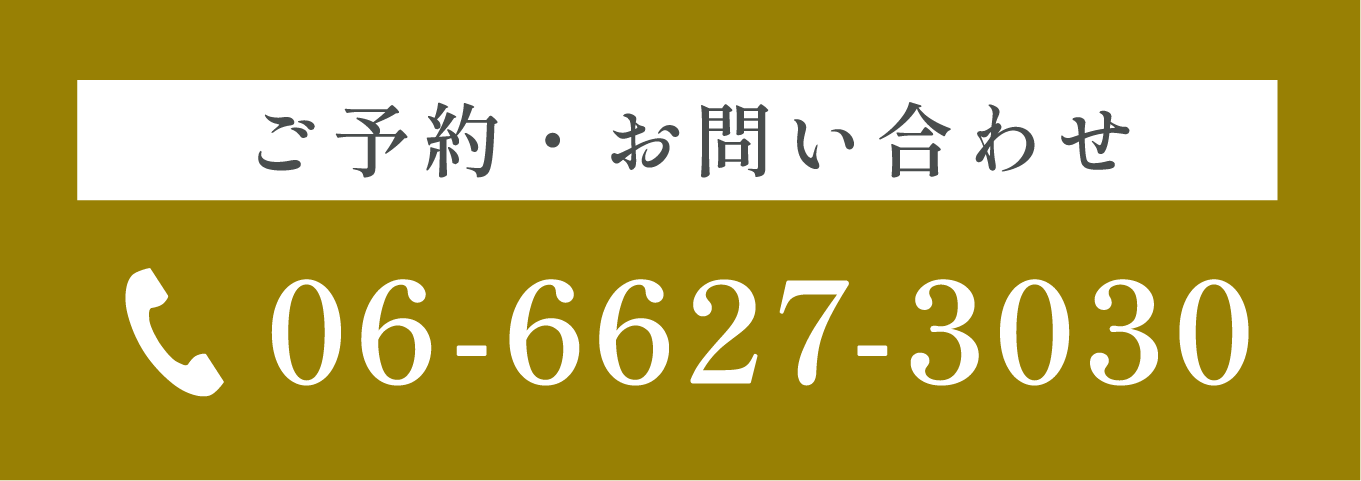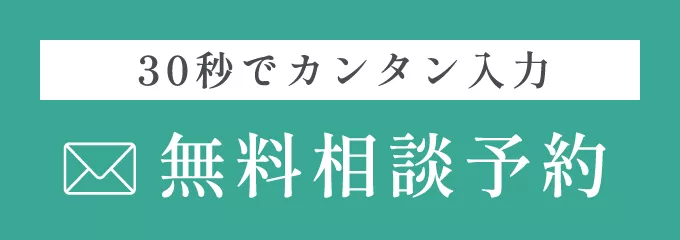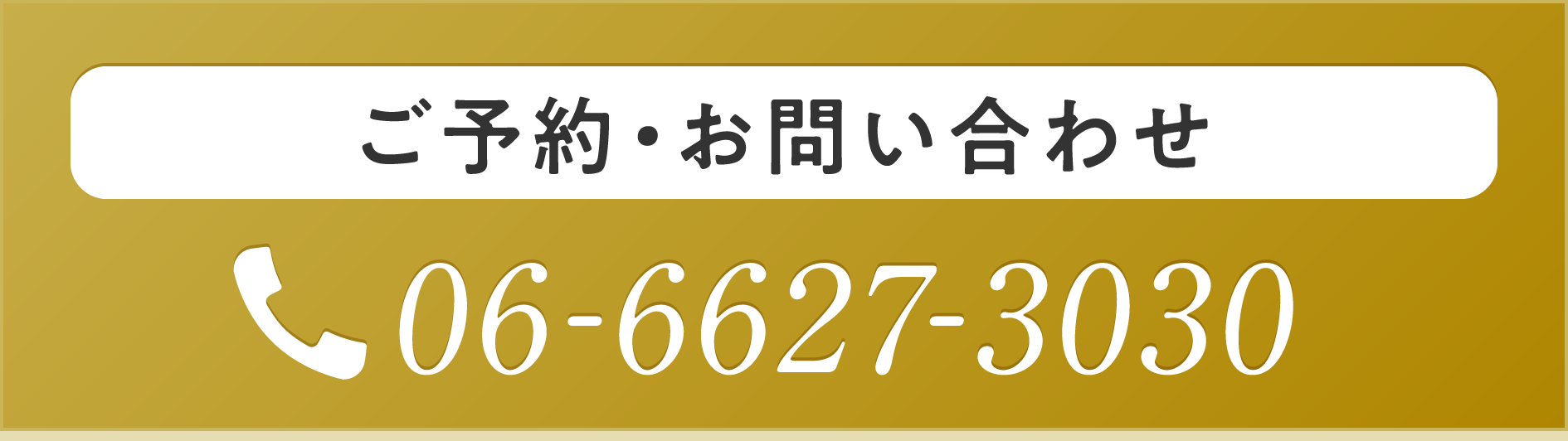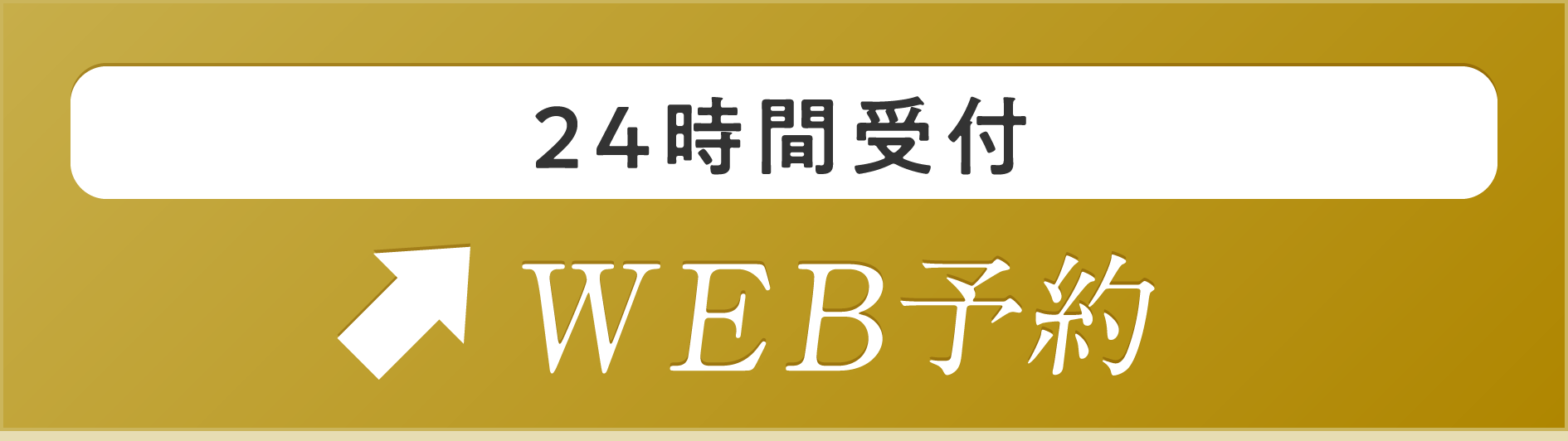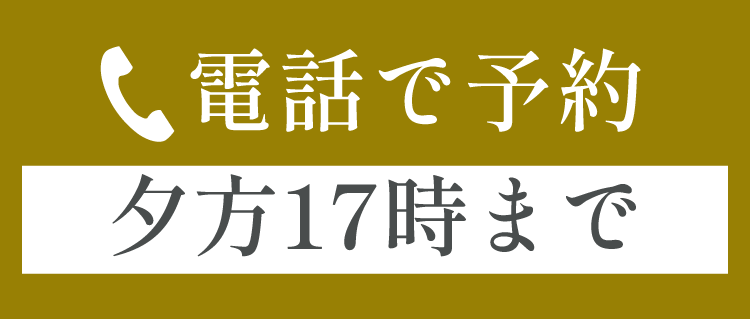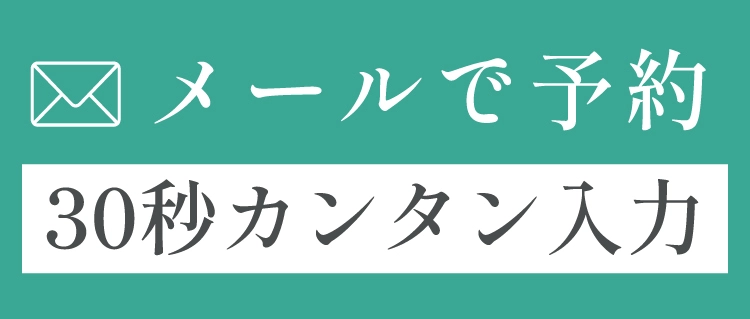インプラントは老後になると悲惨なことになる」そんな不安を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
確かに、インプラントは天然歯に近い噛み心地や見た目を再現できる一方で、加齢に伴う骨や歯茎の変化、全身疾患、介護や入院といった生活環境の影響を受けやすい面があります。
そのため、適切な設計や管理が行われないまま治療を受けると、将来的にトラブルや再治療につながることがあるのです。
しかし実際には、老後に「悲惨」となるかどうかは、治療の計画やメンテナンス体制次第です。
初めから将来を見据えて設計・材料を選び、定期的なケアを続けることで、老後も快適にインプラントを使い続けることは十分に可能です。
本記事では、「なぜインプラントが老後に悲惨と言われるのか」、その原因と対策、さらに長期的に安心して治療を受けるためのポイントについて、インプラント治療を専門的に行う当院院長の岩下が詳しく解説いたします。
目次
なぜ「インプラントは老後が悲惨」と言われるのか
インプラントは、天然歯に近い見た目と咀嚼機能を再現できる治療法として、多くの患者様に選ばれています。しかし、老後になると口腔や全身の状態が大きく変化するため、場合によっては「悲惨」と表現されるようなトラブルにつながる可能性があるのです。
まず、高齢になると歯茎や顎骨が加齢によって吸収・低下し、歯周病や虫歯の進行リスクが高まります。唾液の分泌量も減少するため、口腔内の細菌環境が悪化しやすく、誤嚥性肺炎や全身疾患(糖尿病・心疾患など)にも影響を及ぼすケースがあります。また、体力や認知症の進行によってセルフケアが難しくなると、メンテナンス不足からインプラント周囲炎が進行し、再治療や撤去が必要になることも考えられます。
さらに、老後は通院が制限されることも大きな課題です。定期的な歯科医院での診療やプロによるクリーニングが難しくなると、トラブルを早期に発見できず、症状が重症化してしまうリスクが高まります。特に介護施設や入院時には、スタッフがインプラントの清掃や管理に十分対応できない場合があり、患者様ご自身やご家族にとって大きな負担となりかねません。
もちろん、インプラントには入れ歯やブリッジと比較して大きなメリットもあります。噛み心地や発音が自然で、栄養摂取や会話の質を維持しやすい点は、生活の質を高めるうえで非常に有効です。しかし、そのメリットを長く享受するためには、老後特有のリスクや費用面での注意点を理解したうえで、治療法を検討することが欠かせません。
当院ではCTによる精密診断や外科的手術の計画段階から、将来を見据えた設計・管理を徹底しています。インプラントは「絶対だめ」という治療ではなく、正しい方法と定期的なケアを行えば高齢になっても十分に快適に使い続けられるものです。大切なのは、歯科医師とともに長期的な視点で治療を選択することなのです。
老後にインプラントで起こりやすいトラブル
インプラントは適切に管理されていれば長期的に快適に使える治療法ですが、年齢を重ねるにつれてさまざまなトラブルが生じる可能性があります。高齢になると身体機能や口腔環境が変化し、定期的な通院や歯磨きといった基本的なケアが困難になるケースも少なくありません。結果として、インプラント周囲に炎症が起こり、歯周病のように骨を失うリスクが高まるのです。
また、老後は認知症や寝たきりなど要介護状態に移行することもあり、ご自身で手入れができなくなる場合があります。清掃が不十分になると、感染や炎症が進行して除去や再手術といった外科的処置が必要になることもあります。これは患者様ご本人にとっても大きな負担であり、家族や介護スタッフのサポートが不可欠となります。
さらに、医院への通院が難しくなると、定期診療やプロによるメンテナンスを受けにくくなる点も大きな問題です。特に高齢の方は徒歩での通院が困難になったり、予約が取りにくくなったりと、継続的なケアが途絶えるリスクが高まります。その結果、将来にわたり快適に使えるはずのインプラントが「悲惨」と言われる状況につながってしまうのです。
もちろん、インプラントには入れ歯やブリッジと比較したときの大きなメリットもあります。天然の歯に近い見た目や噛み心地を維持でき、食事や会話の質を高める点は老後の生活において大きな価値があります。一方で、年齢や健康状態によっては別の治療法を検討する方が安心な場合もあるため、歯科医師とよく相談し、自分に合った治療方法を選択することが大切です。
老後にインプラントを快適に使い続けるためには、起こりやすいトラブルや注意点を理解したうえで、予防と定期的なケアを徹底することが不可欠です。当院では患者様一人ひとりの将来を見据えた対策を講じ、長期的な安心につながる診療体制を整えています。
インプラント周囲炎のリスク増加
インプラント治療を受けた後、最も注意すべきトラブルのひとつが「インプラント周囲炎」です。これは、天然歯に起こる歯周病とよく似た炎症で、歯茎や顎の骨が細菌感染によって破壊され、インプラントの安定性を失わせてしまう病気です。
特に加齢によって免疫力が低下すると、炎症が進行しやすくなります。日常的な歯磨きや自宅でのケアが不十分になると、定期的な歯科医院でのメンテナンスを受けていてもリスクは増加し、場合によっては外科的な手術が必要になるケースもあります。
インプラント周囲炎が厄介なのは、初期段階では症状が軽いため気づきにくい点です。歯茎の腫れや出血が見られても「虫歯ではないから大丈夫」と思い込み、治療が遅れてしまう患者様も少なくありません。その結果、炎症が深部まで進行し、インプラントを除去せざるを得なくなる可能性があるのです。
当院では、インプラント周囲炎の予防を最重要課題の一つと考えています。治療後も定期的にクリニックでの検診・クリーニングを行い、口腔内の細菌の状態をチェックすることが大切です。歯科医師と連携しながら適切な治療法や予防策を講じることで、インプラントを長期的に維持し、老後も快適に使い続けることが可能になります。
咬合力や骨量の低下
インプラントは顎の骨にしっかりと結合してこそ、その機能を十分に発揮します。しかし高齢になると、骨密度の低下や骨吸収が進行し、インプラントの安定性が損なわれるリスクが高まります。特に骨粗鬆症や糖尿病といった全身の病気は骨の強度や回復力に大きく影響を及ぼし、再治療や骨造成が難しくなる可能性もあります。
咬合力が低下すると、咀嚼機能そのものにも支障が生じます。食事から十分な栄養を摂取できなくなれば、全身の健康状態の悪化にもつながりかねません。カルシウム不足や咀嚼刺激の減少は骨密度の維持に悪影響を与え、悪循環を生むことになります。こうした変化は患者様ご自身が気づかないうちに進行するため、定期的な歯科での診療やチェックが欠かせません。
当院では、骨粗しょう症や歯周病など全身や口腔の状態を踏まえた治療計画を行っています。インプラントを長期的に維持するためには、食事や生活習慣の改善、適度な運動による骨折予防、さらには栄養バランスの取れた食事内容の検討が必要です。高齢者であっても咬合機能を維持できれば、健康寿命の延伸にも大きく寄与します。
骨量の低下は避けられない加齢変化の一つですが、適切な予防とケアによってリスクを軽減することは可能です。歯科医師と連携し、患者様一人ひとりに合った方法で骨や咬合力を維持することが、老後においてインプラントを快適に使い続ける鍵となります。
全身疾患との関係
インプラント治療は口腔内だけでなく、全身の健康状態とも深く関わっています。特に糖尿病や骨粗鬆症といった疾患は、骨の治癒能力や免疫機能に影響を与え、インプラントの結合や長期的な安定性にリスクを及ぼします。血糖コントロールが不十分な場合には、感染や炎症が悪化しやすく、手術後の回復が遅れる可能性もあります。
また、高血圧や心疾患の患者様が服用している「血液をサラサラにする薬」などの投薬も治療計画に制限を加える要因となります。抜歯や外科手術を伴うインプラント治療では出血リスクが高まるため、歯科と内科が連携して適切な診療体制を整えることが必要です。
当院では、インプラント治療を希望される患者様に対して、全身の健康状態を丁寧に確認し、必要に応じて主治医と情報を共有しながら治療方針を決定しています。疾患や服薬の有無を正しく把握したうえで計画を立てることで、手術の安全性を確保し、長期的に安心してインプラントを維持することが可能になります。
老後でもインプラントを快適に使い続けるための条件
インプラントは入れて終わりではなく、その後の過ごし方によって寿命が大きく変わります。特に高齢期を迎えたときに快適さを維持するには、治療の設計段階からの工夫、日々のケア、そして全身の健康管理までを含めた総合的な取り組みが重要です。
ここからは、実際に当院が大切にしている「設計」「メンテナンス」「全身管理」という3つの視点について、順に解説していきます。
①計画段階から将来を見据えた設計
インプラントは一度手術を行えば長期間使える治療法ですが、その寿命や快適性は「設計段階」で大きく左右されます。治療前の診断やシミュレーションが不十分だと、将来的に清掃が難しい形態になったり、骨量不足で再治療が必要になる可能性があります。そのため、事前に口腔環境を精密に把握し、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立てることが欠かせません。
具体的には、十分な骨幅や歯茎の厚みを確保することが重要です。必要に応じてGBR(骨造成)やFGG(歯肉移植)といった外科的処置を併用することで、安定性の高い土台をつくります。また、噛み合わせや咬合力のバランスを考慮し、将来にわたってセルフケアしやすい位置や角度にインプラントを配置することも大切です。
当院では、人工歯の素材にレジンを使用せず、ジルコニアやセラミックなど長期耐久性に優れた材料を採用しています。これにより、見た目の審美性だけでなく、強度・清掃性の両面から安心感を確保しています。さらにCTスキャンやデジタル技術を活用した精密診断を行い、治療の成功率を高めています。
将来の健康状態や生活環境は患者様によって異なります。だからこそ、歯科医師が長期的な視点で計画を立て、メンテナンスのしやすさや全身疾患との関係まで考慮することが、インプラントを長持ちさせる最大の条件です。設計段階から丁寧に対応することで、術後の負担を軽減し、老後も快適な咀嚼や会話を維持できるのです。
②定期的なメンテナンスの徹底
インプラントを長持ちさせるためには、治療直後だけでなく、その後の定期的なメンテナンスが欠かせません。天然歯と同様に、インプラントの周囲にも歯垢やプラークがたまり、細菌感染によって炎症や歯周病のような症状が進行するリスクがあるためです。
一般的には、3〜6か月ごとに歯科医院でのクリーニング(PMTC)やチェックを受けることが推奨されています。歯科衛生士によるプロフェッショナルケアでは、歯ブラシやデンタルフロスでは除去できない汚れを取り除き、噛み合わせや人工歯の状態をレントゲンや診査で確認します。こうした診療を定期的に行うことで、インプラントの寿命を延ばし、長期的な安心につなげることができます。
一方で、患者様ご自身による日々のセルフケアも同じくらい重要です。歯間ブラシやデンタルフロスを使ったブラッシング、歯茎周囲の丁寧な清掃を習慣化することで、トラブルの原因となる細菌の繁殖を防ぎます。当院では患者様一人ひとりの口腔環境に合わせ、最適な清掃方法や使用するブラシの種類を歯科医師・歯科衛生士が指導しています。
定期検診とセルフケアを両立することで、炎症や虫歯といった問題を早期に発見し、再治療や手術といった大きな負担を回避することが可能になります。禁煙や生活習慣の改善も含め、全身の健康とあわせて取り組むことが、インプラントを快適に維持する最大のポイントです。
③全身の健康管理
インプラントを長期的に快適に維持するためには、口腔だけでなく全身の健康状態を整えることが欠かせません。糖尿病や骨粗鬆症といった疾患は、骨密度や免疫力に影響を及ぼし、手術後の回復やインプラント周囲の安定性を左右します。特に糖尿病の患者様では炎症や歯周病が進行しやすく、インプラントの寿命を縮めるリスクがあるため、定期的な検診や内科との連携が重要です。
また、日常生活における食生活や運動習慣も大きな役割を果たします。カルシウムやタンパク質を意識した食事は骨の強度を維持し、適度な運動は血流改善と全身の機能回復に寄与します。さらに、喫煙や過度の飲酒、強い歯ぎしりなどは口腔や全身に悪影響を与えるため、生活習慣の改善が予防の鍵となります。
当院では、インプラント治療後も定期的な歯科検診とクリーニングを通じて、患者様一人ひとりの健康状態をチェックしています。必要に応じて専門家のアドバイスを取り入れ、セルフケアや生活習慣の調整をサポートすることで、トラブルの可能性を最小限に抑えています。
全身の健康管理を継続的に行うことは、インプラントの成功率や耐久性を高めるだけでなく、日常生活の快適さや自信にも直結します。歯科医師と連携しながら、ご自身の体調やライフスタイルに合った健康管理を実践することが、長期間インプラントを安心して使い続けるための最も効果的な方法なのです。
老後の介護や入院時のインプラント管理
インプラントは日常生活だけでなく、介護や入院といった特別な環境下でも適切な管理が求められます。高齢になると、施設スタッフや医療従事者に日々の清掃やケアを任せる場面が増えるため、セルフケアが難しい場合でも清掃が不十分にならない体制を整えることが大切です。
また、入院や全身麻酔を伴う手術の前には、口腔内の状態をしっかりと管理しておく必要があります。場合によっては抜歯やインプラントの撤去といった判断が求められるケースもあり、歯科医師と医科の連携が不可欠です。
ここからは、介護施設での清掃対応、そして入院時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
介護施設での清掃対応
高齢になり介護施設で生活するようになると、インプラントのセルフケアは困難になりがちです。患者様ご自身で歯ブラシや歯間ブラシを使った清掃ができなくなると、汚れや細菌が周囲に蓄積し、歯周病や炎症が進行するリスクが高まります。特に認知症や寝たきりの方では、口腔ケアが不十分なまま生活が続き、全身疾患に影響する可能性もあります。
しかし、介護スタッフの多くは天然の歯や入れ歯に比べて、インプラントの清掃方法について十分な知識を持っていないのが現状です。そのため「見た目はきれいでも実際には清掃が不十分」というケースが起こりやすく、患者様の健康や栄養摂取に影響することもあります。
このようなトラブルを防ぐには、歯科医師や歯科衛生士が介護者へ適切な指導を行い、清掃器具や方法を共有することが重要です。例えば、歯間ブラシや専用ブラシを用いた清掃、フロスの使い方、必要に応じた訪問診療の活用など、施設全体で取り組む体制を整える必要があります。
インプラント治療をした方の老後が悲惨にならないためには、介護施設やご家族と連携して患者様一人ひとりの健康状態や生活習慣に合わせたケアを行うことや、定期健診や訪問診療を組み合わせることで、施設に入ってもインプラントを快適に維持し続けられる環境をつくることが必要です。
入院時の対応
高齢になって入院や全身麻酔を伴う手術を受ける際には、インプラントも含めた口腔管理が非常に重要です。患者様の健康状態によっては、炎症や細菌感染が全身に悪影響を及ぼす可能性があるため、事前に歯科医師によるチェックを受けることが推奨されています。
特に、抜歯やインプラントの撤去が必要になるケースもあり、その判断は症状や持病の有無、手術の内容によって異なります。例えば、強い炎症や骨粗鬆症などの疾患を抱えている場合、傷口の回復が遅れるリスクが高いため、早めに対応を検討しなければなりません。
入院中は普段のように歯磨きや清掃が行えず、汚れが残りやすい環境にあります。その結果、腫れや痛みが長引く恐れがあるため、医師や歯科と連携した管理が欠かせません。処方される薬との兼ね合い、血流や免疫力への影響も考慮する必要があります。
当院では、患者様が入院される場合には主治医や医科の担当医と情報を共有し、安全性を第一にした対応を徹底しています。術前・術後の流れや注意点を明確に説明し、不安を軽減することで、入院期間中も安心して過ごせる体制を整えています。
老後を見据えたインプラントの経済的な負担と長期コスト
インプラントは天然歯に近い機能や見た目を再現できる大きなメリットがありますが、その分、費用面での負担も無視できません。特に老後は収入が限られる中で、再治療やメンテナンスにかかる費用が発生する可能性があり、計画的に備えておくことが重要です。
また、入れ歯やブリッジと比較した場合、初期費用だけでなく長期的なコストの推移にも違いがあります。将来を見据えた治療選択を行うためには、それぞれの特徴を理解し、生活設計に合った方法を検討する必要があります。
ここからは、老後に直面しやすい「再治療・メンテナンス費用」と「長期的なコスト比較」について詳しく解説します。
老後のインプラントの再治療・メンテナンス費用
インプラントは一度埋入すれば長期間使える治療法ですが、加齢に伴う歯茎や骨の低下、周囲の炎症などが原因で、再治療や部品の交換が必要になる場合があります。特に高齢になると持病や体力の低下によって治療後の回復が遅れやすく、状況によっては外科的な処置や除去を検討せざるを得ないケースもあります。
こうした再治療や修理には、治療費の負担が伴います。インプラントは原則として健康保険の適用外であるため、費用は自己負担となります。保証期間を過ぎた場合はさらに高額になることも多く、老後に収入が限られる状況では大きな不安要素となりかねません。患者様やご家族が安心して治療を続けられるよう、あらかじめ計画的に準備しておくことが重要です。
また、インプラントを長持ちさせるには、定期的なメンテナンスを受け続けることが不可欠です。歯科医院でのクリーニングや診査は追加の費用が発生しますが、トラブルを早期に発見して大掛かりな再手術を回避するうえで非常に効果的です。結果的に「短期的な費用を惜しまず、長期的な出費を抑える」という視点が、老後のインプラント維持には欠かせません。
当院では患者様の健康状態や生活環境を考慮し、一人ひとりに合わせたメンテナンス計画をご提案しています。再治療が必要になるリスクを最小限に抑え、老後も安心して噛める環境を維持するために、早期からの準備と継続的なケアをおすすめしています。
インプラントと他の治療の長期的なコスト比較
インプラント治療は初期費用が比較的高いのが特徴ですが、長期的に見た場合には入れ歯やブリッジと異なるコスト構造を持っています。例えば、入れ歯は健康保険が適用されるため初めは安価に治療を受けられる一方で、数年ごとに作り直しや調整が必要になり、通院や手入れの負担も増えていきます。ブリッジも同様に、支えとなる周囲の歯を削る必要があり、時間の経過とともに虫歯や歯茎の状態悪化といった問題が起こりやすい点がデメリットです。
一方、インプラントは天然の歯に近い安定感と機能を長期間維持できるため、再治療の頻度が少なく、結果的に長持ちしやすいという大きなメリットがあります。ただし健康保険の適用外であり、部品交換やメンテナンスに自由診療の費用がかかる点は理解しておく必要があります。
当院では、患者様の年齢や歯を失った部位、噛み合わせの状態などを考慮し、インプラント・入れ歯・ブリッジのシミュレーションを行っています。これにより「短期的には費用を抑えたい方」「長期的に快適さと安定を優先したい方」など、それぞれのライフスタイルや健康状態に合った治療選択が可能になります。
初期費用の高低だけではなく、通院回数や手入れの手間、長期的な快適さや噛む力の維持といった要素まで含めて比較検討することが、老後に後悔しない治療を選ぶための大切な視点です。
インプラント以外の治療選択肢と老後の過ごし方
インプラントは多くの患者様に選ばれる治療法ですが、必ずしもすべてのケースに最適とは限りません。加齢による体力や健康状態、生活環境の変化によっては、入れ歯やブリッジといった他の治療法が適している場合もあります。
入れ歯やブリッジは取り外しやすさや調整のしやすさといった利点があり、インプラントと併用する選択肢も存在します。また、老後のライフスタイルに合わせて、通院の頻度や長期的な費用バランスを考慮した治療計画を立てることが大切です。
ここからは「入れ歯・ブリッジの活用」と「老後のライフスタイルに合わせた治療戦略」について、具体的に解説していきます。
高齢の方の入れ歯・ブリッジの活用
歯を失った場合の治療法として、入れ歯やブリッジは現在でも多くの患者様に選ばれています。特に高齢者の方にとっては、取り外しができる義歯の利便性や、保険診療の適用によって初期費用を抑えやすい点が大きな特徴です。通院や手入れの方法に合わせて選択できるため、体力や健康状態に不安を抱える方にも適した治療法といえます。
入れ歯は清掃や手入れがしやすく、毎日の生活で負担を軽減できる点がメリットです。一方で、金属のバネによる見た目の違和感や、噛む力が天然歯やインプラントに比べて劣るといったデメリットも存在します。ブリッジは固定式で自然な見た目を再現できる一方、支えとなる周囲の歯を削る必要があり、虫歯や歯茎への負担が大きくなる可能性があります。
当院では、患者様の年齢や健康状態、生活習慣を考慮しながら、入れ歯・ブリッジ・インプラントの中から最適な方法をご提案しています。場合によっては「インプラントと部分入れ歯を併用する」といった治療計画をとることで、見た目の自然さとメンテナンス性を両立できるケースもあります。
「自分に合った治療法が分からない」と感じる方は、まずは歯科医へ相談し、将来のライフスタイルを含めて検討することが大切です。高齢になっても快適な咀嚼や会話を保つために、入れ歯やブリッジを積極的に活用する選択肢は有効なのです。
老後のライフスタイルに合わせた治療計画
高齢者にとって、治療をどのように選択するかは単なる口腔の問題にとどまらず、日常生活や健康状態全体に大きな影響を及ぼします。老後は体力や免疫力の低下により、通院が困難になったり、介護や家族のサポートが必要になる場合も少なくありません。そのため、治療法を選ぶ際には「長期的なコスト」「通院頻度」「将来的な負担」を含めた計画を立てることが不可欠です。
例えば、入れ歯は取り外しが可能で管理しやすく、初期費用も比較的抑えられるため、介護環境に移行した後も柔軟に対応できる利点があります。一方、インプラントは天然の歯に近い快適さを維持できるものの、定期的なメンテナンスやクリーニングが必要で、長期的には費用が高くなる場合もあります。ブリッジは見た目の自然さを確保しやすい反面、周囲の歯に負担をかけるため、状態によっては再治療や除去が必要となるケースもあります。
当院では、患者様一人ひとりの健康状態や生活環境を考慮しながら、歯科医師が最適な治療計画をご提案します。老後のライフスタイルや将来の変化を踏まえて相談することで、「どの治療法を選べば安心して長く快適に過ごせるか」という疑問に、より現実的な答えを見いだすことができます。
治療の選択肢を比較し、医療的な安全性と生活の質の両立を目指すことが、老後の歯科治療において最も重要な視点なのです。
まとめ:インプラントは老後を見据えた設計と管理が重要
インプラントは、見た目の自然さや咀嚼機能の回復といった大きなメリットを持つ一方で、老後に入ると骨や歯茎の変化、全身疾患、介護や入院といった生活環境の影響を受けやすい治療法です。しかし、それが「悲惨」な結果につながるかどうかは、最初の設計から日々のメンテナンス、そして全身の健康管理まで、どれだけ将来を見据えた取り組みができるかにかかっています。
計画段階での慎重な診断と設計、定期的なメンテナンス、そして患者様ご自身と歯科医師の二人三脚による健康管理。この3つを徹底することで、インプラントは高齢になっても十分に快適に使い続けられるのです。
「長く安心して使えるインプラント治療」を実現するために、老後のライフスタイルや経済的な側面も含めて治療を検討し、信頼できる歯科医院で相談することをおすすめします。当院でも一人ひとりの将来を見据えた治療計画をご提案し、患者様が老後も安心して笑顔で過ごせるようサポートしてまいります。
【執筆・監修者】

帝塚山Smile Design Clinic(スマイルデザインクリニック)
院長:岩下太一(歯学博士)
ITI日本支部公認インプラントスペシャリスト認定医
オステムインプラントインストラクター 講師
日本審美歯科学会 認定医
他、所属学会、認定資格多数
充実した無料カウンセリング

初回費用は一切かかりません。安心してご相談ください。
当院では患者様に安心してインプラント治療を受けて頂くために、無料カウンセリングを充実させております。お口の中のお写真やレントゲン写真、場合によってはインプラントの骨を確認するためのCT撮影も無料で行います。もちろん、初回なので一切費用はかかりません。患者様に今のお口の状態を知って頂き、納得してインプラント治療を受けて頂くことが私たちの喜びです。
ITIインプラントスペシャリスト認定医

~ 世界レベルのインプラント治療をあなたへ ~
帝塚山スマイルデザインクリニックの院長はインプラント治療を他の歯科医師に教えるインストラクターの指導的立場として歯科界に貢献しております。また世界的に有名なインプラント学術団体のITI(International Team for Implantology)の日本支部公認インプラントスペシャリストの認定医でもあります。他院で難しいと言われたインプラント治療でも当院では十分に対応できる技術があります。